| ベルグソン(Henri-Louis Bergson 1859-1941)の哲学を、うきうき楽しみながら読んでみたいと思う。というのも、哲学の書物には、うんうん唸りながら読むタイプのものと、うきうき楽しみながら読むタイプのものがある。ヘーゲルの書物がうんうん唸りながら読むタイプの最たるものだとすれば、ベルグソンの書物はうきうき楽しみながら読むタイプを代表するものだろう。要するにベルグソンの哲学は、読む人をして楽しませてくれるのである。 | 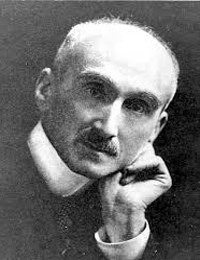 |
| 知の快楽 | 哲学の森に遊ぶ | |
| HOME | ブログ本館 | 東京を描く | 日本文化 | 英文学 | 仏文学 | プロフィール | 掲示板 | ||
ベルグソンの哲学 |
| ベルグソン(Henri-Louis Bergson 1859-1941)の哲学を、うきうき楽しみながら読んでみたいと思う。というのも、哲学の書物には、うんうん唸りながら読むタイプのものと、うきうき楽しみながら読むタイプのものがある。ヘーゲルの書物がうんうん唸りながら読むタイプの最たるものだとすれば、ベルグソンの書物はうきうき楽しみながら読むタイプを代表するものだろう。要するにベルグソンの哲学は、読む人をして楽しませてくれるのである。 | 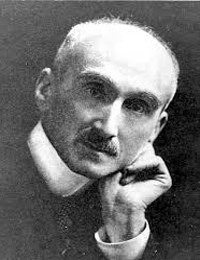 |
ベルグソン以外にも楽しく読める書物はある。近代以降に限っても、スピノザやライプニッツは楽しく読める、だがベルグソンの書物はレベルを超えた楽しさを与えてくれる。その最大の理由は、かれの文章の流麗さと感性的な色合いだろう、それを小生は文章のつやとか色気とか言いたいが、その色気に満ちた文章をベルグソンは書く。その色気ある文章を以て、どんな人間にとっても深い関心を持っているようなことについて語ってくれる。うきうきと楽しまないではいられないではないか。 ベルグソンの文章は息の長いことが特徴だ。一節ごとの文が長い上に、段落あたりの字数も非常に長い。だいたい哲学者が書く文章は、息の長いのが特徴で、一段落が数ページにわたるものも珍しくないが、なかでもベルグソンの文章はとりわけ長い。だから読むほうはかなりの緊張を強いられるはずなのだが、ベルグソンに限ってはそうした緊張は感じないで、すらすらと読み進めることができる。哲学書の文章の中では、デカルトの文章がそうした性質のものだったが、デカルトの場合は、明晰判明な文章を以て明証的で判然とした事象を語っていた。それに対してベルグソンは、明晰判明な文章を以て書くことはデカルト同様だが、かれの場合は、その明晰判明な文章を以て、不分明で曖昧模糊とした事柄を書くという傾向がある。そのミスマッチが、ベルグソンの書物に独特の味わいをもたらし、その味わいに読者は酔いしれる。うくうきと楽しみながら読まざるを得ないのだ。 不分明で曖昧模糊というような言い方をしたが、じっさいベルグソンの哲学はそういった対象をテーマにしたものである。そのことはベルグソン自身はっきりと明言している。ベルグソンは哲学を科学と比較して、科学が明晰分明な論理によりながら世界を分節化された相において見ることを特徴とするのに対して、哲学は分節化以前の渾沌とした相をそのままに取り上げるのだと言う。分節化以前の渾沌とした相とは、意識に直接与えられたままの直観的な内容という意味である。科学はその直観からスタートして、その直観に細工を加えながら、暫時高度な概念的な思考に移っていく。それに対して哲学は、直観の内容をそのままに受け取り、それに下手な細工を加えないで、ありのままに楽しむところに成立すると考えた。 このように、対象を意識に直接与えられた直観の内容として捉え、その直観からはじめる考え方を直観主義とか経験主義とか言うことがある。そうした経験主義的な哲学は、十九世紀の末期にカント哲学の復権運動が起こったときに盛んになったもので、新カント主義と言われることもある。新カント主義の特徴は、直観に存在の基盤を認めることで、直観における対象の明晰性が対象の存在を基礎付けるという見方をする。西田幾多郎の哲学も、そうした新カント的な直観主義に強い影響を受けていて、直観から出発しながら、さまざまな理屈を弄して、独自の認識論と存在論を展開した。その西田がもっとも親近感を抱いていた西洋哲学者はベルグソンだった。西田はベルグソンの直観主義哲学に、自分の思想との類似を見たのだった。といっても、西田がベルグソンの弟子格にあたるというわけではない。両者は時代の思想的雰囲気を共有していたと言うべきだろう。 ベルグソンの哲学を直観主義と言ったが、それにはベルグソンならではの特徴的な内容が含まれている。それを単純化して言うと、唯心論的な存在論と、ユダヤ教的な神秘主義ということになる。ベルグソンがユダヤ人であることはよく知られているが、そのかれの思想がユダヤ教を強くこだまさせる部分を含んでいることはあまり注目されていない。それは、ベルグソン自身キリスト教を強く擁護しているところからきていると思うのだが、ベルグソンがキリスト教に言及しているときには、かならずユダヤ教との関連において語っている。ベルグソンにとってキリスト教とは、ユダヤ=キリスト教なのである。そのユダヤ教には独自の神秘主義がある。その神秘主義を哲学の分野に持ち込んだのはベルグソンがはじめてではないか。無論キリスト教世界で、そんなことを公然と行うわけにはいかない。だからこっそりと行った。つまりキリスト教のベールを被せながらユダヤ教的な思想を語ったということだ。 ベルグソンのユダヤ教的部分に先立って、かれの唯心論的存在論について簡単に言及したい。ベルグソンの哲学の出発点は「時間と自由」だが、これは原題では「意識の直接与件について」となっており、意識の直接与件としての直観の内容をテーマとしている。直観は外に向えば自然を対象とする科学に結びつくが、内に向うと、純粋持続としての自我の把握につながる。哲学とはこの自我を対象とするものである。純粋持続としての自我と、空間的な存在としての自然とは根本的に違っている。従来の哲学は、自我を対象的な自然を扱う科学のモデルにしたがって、あたかも科学の一種であるかのように扱われてきたが、それは間違いだ。科学と哲学とは、異なった対象を扱い、その方法論も異なっている。まったく質を異にしたものなのである。科学には科学固有のものを、哲学には哲学固有のものを、というのがベルグソンの基本的な立場だった。 哲学の対象である自我の本質は、時間性としての純粋持続であるというのがベルグソンの主要命題である。純粋持続とは文字通り持続そのもののことで、その特徴は途切れることなく連続しているということである。常識的な考えでは、吾々の意識は現在に局限されており、過去の出来事に関する意識は記憶としてよみがえるほかは消滅して存在しない状態にあると考える。それに対してベルグソンは、純粋持続は現在から過去に遡って不可分の連続したものとして存在していると考える。ただ普段は意識に上らないので存在しないと思われるだけだ。そうした存在の様態は、無意識を前提にしなければ説明できない。そこでベルグソンは無意識の概念を哲学の重要概念として持ち出すことで、人間の精神の連続的な存在様態を明らかにした。無意識を哲学の要素として本格的に持ち込んだのはベルグソンがはじめてである。それ以前は、無意識は非存在と同様の取り扱いを受けていた。意識にとって存在しないもの、つまり現前しないものは、そもそも存在しないのである。 無意識に注目した思想家としてはフロイトがある。両者はほぼ同時代人で、ベルグソンのほうはフロイトの主張を、かなり早い時期から、ある程度知っていたと思われる。だが両者の間の思想的な影響関係は、あまりなかったようだ。両者がほぼ同じ時期に無意識に注目したのは、おそらくユダヤ神秘主義の影響だろうと思われる。ユダヤ神秘主義には、精神のあり方についての独特の主張がある。西洋の伝統的な哲学、ギリシャ・キリスト教的な思想は、人間の意識の表層部分を舞台として営まれてきた。無意識の入る余地はなかったのである。ところがユダヤ神秘主義は、人間の精神的なあり方を、無意識を含んだ重層的なものとしてとらえ、しかもその精神=心に実在性を認めた。世界とは、この実在する心の生み出したものだとする唯心論的な思想を、ユダヤ神秘主義は含んでいたのである。それをフロイトとベルグソンがほぼ同時に、学問の前面に押し出したというふうに言えるのではないか。 無意識をきっかけとしてユダヤ神秘主義に言及してしまったが、ベルグソンにはそうしたユダヤ神秘主義の影がいたるところにさしている。すでに意識の直接与件を論じた学位論文がそうであったし、精神的な原理としてのエラン・ヴィタールが、人間を含めた世界の進化の要因だと指摘した「創造的進化」がそうであった。そして最晩年の「道徳と宗教の二源泉」は、このユダヤ神秘主義の思想を正面に押し出して、道徳と宗教の起源について語った。そういうふうに見ると、ベルグソンの哲学は、ユダヤ神秘主義を哲学の原理として確定させるための営みだったと言えなくもない。 このプロジェクトでは、そんなベルグソンの哲学を、主要な著作を読み解きながら明らかにしていきたい。 ベルグソンの哲学入門 変化の知覚:ベルグソンを読む 哲学的直観:ベルグソンを読む ベルグソンのウィリアム・ジェームズ論 可能性と事象性:ベルグソンの存在論 哲学の方法:ベルグソンの方法序説 哲学の方法その二:哲学と科学 時間と自由:ベルグソンを読む 時間と自由その二:ベルグソンを読む 物質と記憶:ベルグソンを読む ベルグソンの時間 ベルグソンの無意識 ベルグソンの笑い ベルグソンのエスプリ 創造的進化:ベルグソンの思想 ベルグソンの意識 ベルグソンの存在と無 思考の映画仕掛:ベルグソンの思想 生命のビッグバン:ベルグソン「精神のエネルギー」 ベルグソンの心身二元論 心霊研究へのベルグソンのかかわり 夢についてのベルグソンの議論 誤った再認:ベルグソンを読む 脳と思考についてのベルグソンの議論 道徳と宗教の二源泉:ベルグソンを読む 閉じた社会と開いた社会:ベルグソンの思想 静的宗教と動的宗教:ベルグソンの思想 魔術と神秘主義:ベルグソンの思想 篠原資明「ベルクソン」 ドゥルーズのベルグソン論 |
| HOME |
|
作者:壺齋散人(引地博信) All Rights Reserved (C) 2015-2021 このサイトは、作者のブログ「壺齋閑話」の一部を編集したものである |